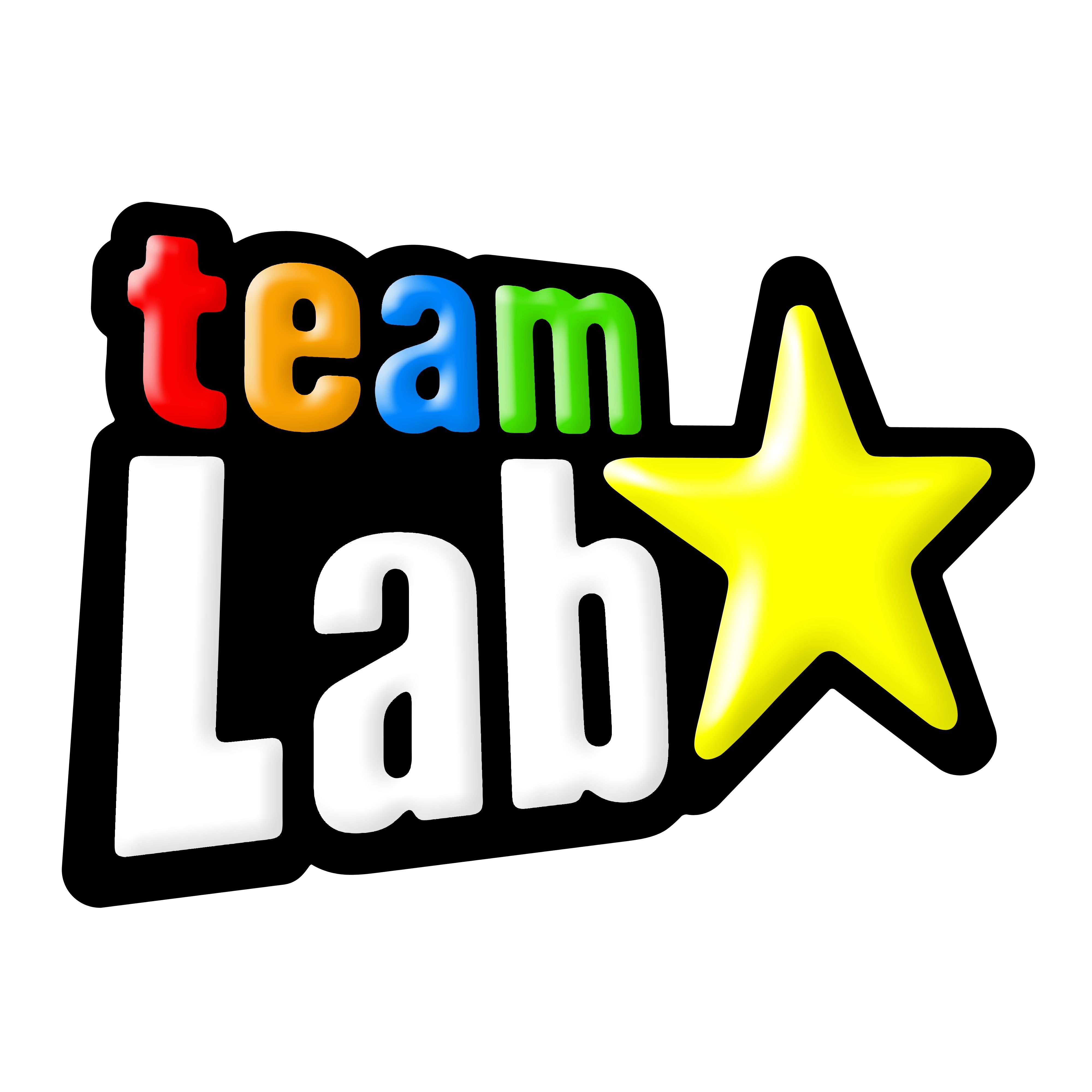オールひめじ・アーツ&ライフ・プロジェクト
- 更新日:
- ID:23985

姫路城

書寫山圓教寺
1) 概要
アートはライフ(命・一生・くらし)に溶け込んでこそ真価を発揮する。姫路市立美術館は、アートのプラットフォームとして、海・島・山・森林・田園、ひめじ全域が擁する地域文化をアートの力で市民ライフの糧として再発見するとともに、新たな姫路の魅力を国内外に発信するアートプロジェクト「オールひめじ・アーツ&ライフ・プロジェクト」を推進する。
本プロジェクトにおいて姫路市立美術館では、姫路の二大文化資源である姫路城と書寫山圓教寺をつなぎ、有形・無形の文化資源の現代的価値を創出・発信する文化クラスターを形成していくことを目指す。そのために新たなプログラムを特別企画展に組み込み、年間を通じて展覧会事業全体を強化する。
2021から2024年の4か年は、「庭園アートプロジェクト」を担う中谷芙二子氏(霧の彫刻家)をはじめ、日比野克彦氏(先端芸術表現領域・アートプロジェクト)、杉本博司氏(メディア横断型現代美術)、チームラボ(デジタルアート)、隈研吾氏(建築・都市デザイン)の各分野の第一人者によって構成されるコア・アーティスト5名を招聘し一連の表現活動として事業を展開する。
2) 主要事業
1. フォーラム(拠点:姫路城、圓教寺、姫路市立美術館)
姫路市立美術館を核としたアートクラスター形成を推進し芸術文化発信拠点としての機能強化を図るためのコア・アーティストによる公開ディスカッションや来場者が自由に参加できるフリートーク、リレーレクチャー等を実施。
アーティスト
- 日比野克彦
- 杉本博司
- チームラボ
- 隈研吾
- 中谷芙二子
| 年度 | テーマ |
|---|---|
| 令和3年度 | 姫路の三大建築美の真髄と可能性~姫路城、圓教寺そして美術館 |
| 令和4年度 | 昔も今も建築は美術です |
| 令和5年度 | 抱一・其一からチームラボへ 江戸琳派の可能性 |
| 令和6年度 | 負けて勝つ城:建築美の勝利とは何か |
2. 庭園アートプロジェクト(拠点:姫路市立美術館)
世界文化遺産・国宝「姫路城」、国登録有形文化財「姫路市立美術館」、「13点の彫刻作品が展示された庭園」が三位一体を成す全国的に見ても稀有な絶景そのものを作品化したインスタレーションを展開する。
| 年度 | アーティスト | テーマ |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 菅野由弘(作曲家)、明珍宗敬(鍛冶師) | 「日本の心象」展第3章「たまはがねの響-音と光のインスタレーション」 |
| 令和4年度 | 中谷芙二子 | 「霧の彫刻 その1:身体との対話」 作品名《白鷺が飛ぶ》 |
| 令和5年度 | 中谷芙二子 | 「霧の彫刻 その2:風景を聴く」 |
| 令和6年度 | 中谷芙二子 | 「霧の彫刻 その3:体・音・光」 |
3. アーティスト・イン・レジデンス(拠点:圓教寺)
「総合芸術の聖地」(圓教寺住職:大樹玄承氏)である圓教寺を拠点とし、姫路市の有形・無形の文化資源をテーマとした滞在型制作や現地でのアーティスト・トーク、ワークショップ、インスタレーション、パフォーマンス、公開制作等を行い、クリエイティブな活動を通じた固有の価値の磨き上げと新たな価値を創出。
| 年度 | アーティスト | テーマ |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 日比野克彦 | 明後日のアートの学校 町も海も山も寺も城も人もつながるプロジェクト |
| 令和4年度 | 杉本博司 | 圓教寺×杉本博司 前期 五輪塔-地 水 火 風 空/後期 能クライマックス-翁 神 男 女 狂 鬼 |
| 令和5年度 | チームラボ | チームラボ 圓教寺 認知上の存在 |
| 令和6年度 | 隈研吾 | 21世紀版〈生き延びるためのデザイン・ワーク〉:これからの用の美 |
4. 招聘作家展(拠点:姫路市立美術館)
アーティスト・イン・レジデンス招聘作家による企画展。姫路城・圓教寺・美術館を創造眼と批評眼の複眼的アプローチで捉えなおして新たな価値を創出し、五感に訴える強度のある展覧会として展開する。
| 年度 | アーティスト | テーマ |
|---|---|---|
| 令和3年度 | - | 文化観光拠点施設認定記念特別展「日本の心象 刀剣、風韻、そして海景」 |
| 令和3年度 | 日比野克彦 | 明後日のアート |
| 令和4年度 | 杉本博司 | 杉本博司展 本歌取り |
| 令和5年度 | チームラボ | チームラボ 無限の連続の中の存在 |
| 令和6年度 | 隈研吾 | 自然とはなにか-隈研吾の建築美学、22世紀へのパースペクティブ |
5. 招聘作家&ザ・ミュージアム・コレクション(拠点:姫路市立美術館)
招聘作家と学芸員の協働によりコレクションを再検証し、招聘作家の作品とのコラボレーションも視野に入れた展開により既存の解釈や価値の更新を試みる。
| 年度 | アーティスト | テーマ |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 日比野克彦 | The Museum Collection Meets HIBINO「展示室で会いましょう」 |
| 令和4年度 | 杉本博司 | 「本歌取り式 名画選————今、交差する 伝統・対話・創造」 |
| 令和5年度 | チームラボ | 超主観空間を考える |
| 令和6年度 | 隈研吾 | The Museum Collection Meets KUMA |
3)招聘作家 プロフィール
日比野 克彦

1958年、岐阜県生まれ。2022年4月より、東京藝術大学学長。岐阜県美術館、熊本市現代美術館館長。日本サッカー協会・社会貢献委員会委員長。1982年東京藝術大学美術学部デザイン科卒業、1982年日本グラフィック展大賞受賞。1984年、東京藝術大学大学院美術研究科修了。1986年シドニービエンナーレ参加。1995年、第46回ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館出品作家に選出される。2016年、芸術選奨文部科学大臣賞(芸術振興部門)受賞。地域の特性を生かし表現として生み出すアートプロジェクト「明後日新聞社 文化事業部/明後日朝顔プロジェクト」(2003~)「アジア代表日本」(2006~)「瀬戸内海底探査船美術館」(2010~)種は船航海プロジェクト」(2012~)等。2015年からは障害の有無、世代、性、国籍、住環境などの背景や習慣の違いを超えた多様な人々の出会いによる相互作用を、表現として生み出すアートプロジェクト「TURN」を監修。2017年度より東京2020公認文化オリンピアードとして実施している。2017年度より「アート×福祉」をテーマに「多様な人々が共生できる社会」を支える人材を育成するプロジェクト「Diversity on the Arts Projects(通称:DOOR)」(2017-)を監修。
杉本 博司

1948年東京生まれ。1970年に渡米、1974年よりニューヨーク在住。活動分野は写真、建築、造園、彫刻、執筆、古美術蒐集、舞台芸術、書、作陶、料理と多岐にわたり、世界のアートシーンにおいて地位を確立してきた。杉本のアートは歴史と存在の一過性をテーマとし、そこには経験主義と形而上学の知見をもって、西洋と東洋との狭間に観念の橋渡しをしようとする意図があり、時間の性質、人間の知覚、意識の起源、といったテーマを探求している。世界的に高く評価されてきた作品は、メトロポリタン美術館(NY)やポンピドゥー・センター(パリ)など世界有数の美術館に収蔵。代表作に『海景』、『劇場』、『建築』シリーズなど。2008年に建築設計事務所「新素材研究所」を設立。MOA美術館改装(2017)、清春芸術村ゲストハウス「和心」(2019)などを手掛ける。2009年に公益財団法人小田原文化財団を設立。2017年10月には構想から20年の歳月をかけ建設された文化施設「小田原文化財団 江之浦測候所」をオープン。伝統芸能に対する造詣も深く、演出を手掛けた『杉本文楽 曾根崎心中』公演は海外でも高い評価を受ける。2019年秋には演出を手掛けた『At the Hawk’s Wel(l 鷹の井戸)』をパリ・オペラ座にて上演。主な著書に『苔のむすまで』、『現な像』、『アートの起源』、『空間感』、『趣味と芸術-謎の割烹味占郷』、『江之浦奇譚』、最新刊に『杉本自伝 影老日記』。1988年毎日芸術賞、2001年ハッセルブラッド国際写真賞、2009年高松宮殿下記念世界文化賞(絵画部門)受賞。2010年秋の紫綬褒章受章。2013年フランス芸術文化勲章オフィシエ叙勲。2017年文化功労者。
チームラボ
チームラボは、アートコレクティブ。2001年から活動を開始。集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、そして自然界の交差点を模索している国際的な学際的集団。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、さまざまな分野のスペシャリストから構成されている。チームラボは、アートによって、自分と世界との関係と新たな認識を模索したいと思っている。人は、認識するために世界を切り分けて、境界のある独立したものとして捉えてしまう。その認識の境界、そして、自分と世界との間にある境界、時間の連続性に対する認知の境界などを超えることを模索している。全ては、長い長い時の、境界のない連続性の上に危うく奇跡的に存在する。ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール、シリコンバレー、北京、メルボルンなど世界各地でアート展を開催。ミュージアム・大型常設展を東京・お台場「チームラボボーダレス」、東京・豊洲「チームラボ プラネッツ」、上海「teamLab Borderless Shanghai」、マカオ「teamLab SuperNature Macao」などで開館した他、今後もハンブルク、ユトレヒトなどでオープン予定。
隈 研吾
1954年生まれ。東京大学大学院建築学専攻修了。東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。1964年東京オリンピック時に見た丹下健三の代々木屋内競技場に衝撃を受け、幼少期より建築家を目指す。大学では、原広司、内田祥哉に師事し、大学院時代に、アフリカのサハラ砂漠を横断し、集落の調査を行い、集落の美と力にめざめる。コロンビア大学客員研究員を経て、1990年、隈研吾建築都市設計事務所を設立。これまで30ヵ国を超す国々で建築を設計し、日本建築学会賞、フィンランドより国際木の建築賞、イタリアより国際石の建築賞、他、国内外でさまざまな賞を受けている。その土地の環境、文化に溶け込む建築を目指し、ヒューマンスケールのやさしく、やわらかなデザインを提案している。また、コンクリートや鉄に代わる新しい素材の探求を通じて、工業化社会の後の建築のあり方を追求している。
中谷芙二子

1933年、北海道札幌市生まれ。父は世界の雪氷学を率いた実験物理学者・中谷宇吉郎(1900-1962)。1957年、アメリカ・イリノイ州ノースウェスタン大学を卒業。初期の絵画制作を経て、ロバート・ラウシェンバーグらが結成した芸術と技術の実験グループ「E.A.T.」に参加。その活動の一環として1970年の大阪万博ペプシ館で、初めての「霧の彫刻」を発表。また、1970年代には日本におけるメディア・アートを先導。社会を鋭く見つめたビデオ作品の制作や、海外作家との交流を推進し、1980年「ビデオギャラリーSCAN」を東京・原宿に創設。日本の若手ビデオ作家の発掘と支援に尽力した。霧の作品は、世界各地で90を超える。2017年にはロンドンのテート・モダン新館で新作を発表。同年、フランス芸術文化勲章コマンドゥール受勲。2018年、第30回高松宮殿下記念世界文化賞彫刻部門を受賞した。2018-19年には水戸芸術館で初めての大規模な個展を開く。続いて日本、アメリカ、ドイツ、フランスで次々に新作を発表。2021年4月に開館した長野県立美術館の前庭に、霧の彫刻《-Dynamic Earth Series I-》が常設された。2022年、ミュンヘンのハウス・デア・クンストで、大規模な回顧展を開催している。2022年から2024年にかけ、姫路市立美術館「オールひめじ・アーツ&ライフ・プロジェクト」コア・アーティストとして、庭園アートプロジェクトを展開する。2022年10月文化功労者に選出。2023年2月ウルフ賞芸術部門受賞。
4)注目情報
5)英語版ページ(English ver.)
お問い合わせ
姫路市 観光経済局 観光コンベンション室 姫路市立美術館
住所: 〒670-0012 姫路市本町68番地25 姫路城東側別ウィンドウで開く
電話番号: 079-222-2288
ファクス番号: 079-222-2290