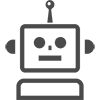資料提供日
令和5年4月7日(金曜日)
問い合わせ先
担当課 姫路文学館学芸課
担当者 徳重
電話番号 079-293-8228
姫路文学館では「姫路文学館紀要 第26号」を発行しました。内容の紹介と購入方法についてお知らせします。
26号は、20年余りにわたった辻善之助「欧米巡歴録」の紹介が完結。例年の第24回司馬遼太郎メモリアル・デーの記録は、文化史・建築史を専門とする井上章一氏の講演など、また25号につづいて「司馬遼太郎の播磨」をテーマとする6篇の評論等を掲載しています。
概要
書籍名
姫路文学館紀要 第26号
編集・発行
姫路文学館
仕様
A5判 本文222ページ
価格
800円
部数
300部(限定)
部数が限定されますので、早めにお求めください。
販売場所
姫路文学館
発行日
令和5年3月31日
26号掲載内容
第24回司馬遼太郎メモリアル・デーの記録
令和4年8月7日、姫路文学館・講堂で開催した第24回司馬遼太郎メモリアル・デーの全内容の記録。
- 講演「司馬遼太郎の歴史観と「鎌倉殿」」 井上章一(国際日本文化研究センター所長)
- 挨拶など 上村洋行(司馬遼太郎記念館館長)、清元秀泰(姫路市長)
講演「司馬遼太郎の歴史観と「鎌倉殿」」の要旨
源義経が美男子、または牛若が美少年であるというイメージは、小学唱歌に「京の五条の橋の上」と歌われたように、日本人の心にふかく浸透しています。ところが、この美しい義経は、室町時代に成立した『義経記』に初めて登場しました。同書では、平泉に向かう牛若は伝説の美女と見まがうほどの美少年になっていますが、もちろん幻想であり、実話ではありません。
事実はどうかというと『平家物語』巻十一の「壇浦合戦」によると、義経の特徴が「むかば」(出っ歯)であるとあります。林羅山や「大日本史」さえ論議した矛盾を司馬遼太郎の長編『義経』は、奥州平泉の少女がいう、出っ歯が「可愛い」という言葉として見事に落としどころを見つけました。
NHKのドラマにあるように鎌倉はテロリズムの横行する町でした。映画の「ゴッドファーザー」のマフィアや「仁義なき戦い」のヤクザの抗争に似ていて、鎌倉幕府の実体は“広域暴力団関東源(みなもと)組”というべきものでした。そうすると北条政子は“極道の妻”になります。ですから、野蛮な、民度の低い武士たちの時代になったといえます。
日本史には、関東武士が律令体制をくずす土地革命を起こしたという関東史観とそれに対して、武士も律令体制、荘園制に取り込まれただけだという学説があります。近年は後者の方が有力になっていますが、司馬遼太郎は関西人でありながら、関東史観をとっていました。凛々しい武士がふぬけの公家たちに代わって新しい世の中をつくった―そうした情操教育を私たちはうけてきました。仁義に生きる“もののふ”を描いて、司馬遼太郎はあれだけの人気作家となったのでしょう。
井上章一(いのうえ しょういち)
1955年、京都市生まれ。国際日本文化研究センター所長。
京都大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了。京都大学人文科学研究所助手、国際日本文化研究センター助教授、教授を経て2020年より現職。専門は建築史、文化史、風俗史。1986年『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、99年『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞受賞。『関西人の正体』『日本に古代はあったのか』『伊勢神宮―魅惑の日本建築』『京都ぎらい』『京都まみれ』など著書多数。
「続・司馬遼太郎の播磨」 玉田克宏(姫路文学館学芸員)
司馬遼太郎は父祖の地、播磨に関しては、播州人を小説に登場させたり、エッセイで論じたりした。そのことをテーマとした前号(25号)の「司馬遼太郎の播磨」の11篇に続く5篇の評論、そしてそれらから漏れた話題を記すメモをまとめた。
司馬が友人関係にあった播州人、俳人の赤尾兜子、歌人の安田章生-どちらも揖保川流域の生まれ―と終生の交わりをもっていたこと。そして大燈国師(宗峰妙超・たつの市出身)のような禅僧、また藤原惺窩(三木市出身)のような朱子学者に対するに好悪をひどく顕わにしたこと―。あるいは立川熊次郎(姫路市勝原区出身)がはじめた講談本の立川文庫と司馬文学の関り、播州人気質への思いといったことを各篇に書いた。
目次
- 12 立川文庫―講談のヒーロー
- 13 藤原惺窩
- 14 揖保川-詩人
- 15 揖保川-禅僧
- 16 播州人気質
- 17 メモ
【参考】前号(25号)掲載分:1 戦車兵―青野ヶ原/2 三島由紀夫/3 生死と『葉隠』/4 出征と念仏/5 清沢満之/6 播州門徒/7 祖父・福田惣八/8 伊和族と秦氏―古代の播磨/9 宮本武蔵/10 蟠桃と松右衛門/11 歴史と文学の間
司馬遼太郎(しばりょうたろう)
小説家。大阪市生まれ。自家が祖父の代まで姫路市広畑に居住。乱世・変革期の群像を描いた『播磨灘物語』、『竜馬がゆく』、『坂の上の雲』などの小説や紀行『街道をゆく』で独自な視点からの歴史解釈を示し、戦後日本における精神文化に大きな足跡を残した。文化勲章受章(1923-1996)。
[資料紹介] 辻善之助「欧米巡歴録 ロンドンとその周辺」
姫路出身の歴史学者・辻善之助(1877から1955)が、欧米における博物館と文化財保護などを視察する旅行において書き残したノートのうち、1分冊の明治44年(1911)10月下旬から12月5日の部分を翻刻、翻訳。今回の紹介で「欧米巡歴録」を読みやすい形態にして公開する作業を5冊のノート全冊について終えることができた。
2001年春の特別展「二人のヨーロッパ 辻善之助と和辻哲郎」において辻の欧米巡歴に光をあて、同展の図録ではさわり部分の抄出にとどまっていた手記ノートの全文の紹介作業を同じ年の紀要4号からはじめた。米欧の11ヶ国の地図や英語、フランス語、イタリア語、ギリシア語、ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ラテン語の辞書で地名、建物、人名、品名などを確認しつつの作業となり、9回の分載、二十年以上の期間にわたってしまった。
今回の内容は、大英博物館のすぐ近くに下宿をさだめた辻が、一ヵ月半のロンドン滞在中、英語のレッスンのかたわらで、同市周辺の博物館、美術館の視察と文化財建造物の見学を精力的に行った記録である。大英博物館では東西の展示品をくまなく見てまわり、とくに日本に由来する美術品を調査、敦煌、于闐の発掘品をもちかえったばかりのスタイン博士に面会する機会を得た。日曜の朝は、ウェストミンスター寺院、セントポール大聖堂などの礼拝に参加しては、キリスト教の宗教儀礼を観察した。イートン、ケンブリッジ、オックスフォードといった学園都市のパブリック・スクール、大学-その図書館など―に足をのばした。
参考1 「欧米巡歴録」各分冊
- 一分冊 (表紙)自十月三十日至二月上旬 〔ロンドンとその周辺、パリ〕
- 二分冊 (表紙)欧米巡歴随感随録 二 自二月上旬至三月十二日 附アメリカ及ロンドン 〔アメリカ、パリ、フランス(中部)、北イタリア、ローマ〕
- 三分冊 (表紙)自三月十三日至五月十九日 (中扉)欧米巡歴随見録 三 明治四十五年三月 〔ローマ、ギリシア〕
- 四分冊 (表紙))自五月二十日至七月九日 (中扉)欧米巡歴随見随感録 四 明治四十五年五月 〔中部・北部イタリア、ウィーン、ミュンヘン、スペイン、南フランス、スイス、ドイツ〕
- 五分冊 (表紙))自七月十一日至八月二十四日 (中扉)欧米巡遊随見随感録 五 明治四十五年七月 〔ドイツ、オランダ、ベルギー、イギリス、フランス〕
参考2 紀要の掲載号の内容
- 4号 アメリカ、パリ
- 6号 南イタリア、ギリシア
- 11号 ドイツ
- 13号 ウィーン・ミュンヘン
- 16号 中部・北部イタリア
- 20号 スペイン・南フランス・スイス
- 21号 オランダ・ベルギー・イギリス・フランス
- 22号 北イタリア・ローマ・フランス(中部)
- 26号 ロンドンとその周辺
辻善之助(つじ ぜんのすけ)
歴史学者。姫路市元塩町生まれ。初代史料編纂所長、東京帝国大学教授。実証的な史学研究の確立に貢献。仏教史、文化史、海外交渉史を専門とした。著作に『日本仏教史』、『日本仏教史之研究』など。文化勲章受章(1877-1955)
姫路文学館紀要26号
お問い合わせ
姫路市役所観光経済局 姫路文学館
住所: 〒670-0021 姫路市山野井町84番地
電話番号: 079-293-8228 ファクス番号: 079-298-2533
電話番号のかけ間違いにご注意ください!