予防活動
- 更新日:
- ID:22961
ページ内目次
火災予防
予防広報
火災をはじめとする各種災害の発生を防止するとともに、その災害を最小限に止めるためには、市民一人ひとりが防災を自らの課題として考え、行動することが必要です。
そのため、新聞・テレビ・インターネット等の民間資力の活用をはじめとして、広報誌、パンフレット、ポスター等の製作・配布、ひめじ防災プラザでの学習・体験、広報車による巡回広報、消防教室等による広報活動を展開し、市民の防火防災意識の高揚を図っています。
火災予防行事等の年間実施状況
春・秋季火災予防運動をはじめ、危険物安全週間、防災の日等のあらゆる機会を捉え、各種防火防災行事を幅広く展開し、市民、各種団体、事業所等に対し、火災予防思想の普及を図っています。
| 行事名 | 実施日 |
|---|---|
| 防災とボランティアの日 (週間) | 1月17日 (1月15日から1月21日) |
| 文化財防火デー | 1月26日 |
| 春季全国火災予防運動 | 3月1日から3月7日 |
| 危険物安全週間 | 6月第2週(日曜日から土曜日までの1週間) |
| 国民安全の日 | 7月1日 |
| 防災の日(週間) | 9月1日 (8月30日から9月5日) |
| 119番の日 | 11月9日 |
| 秋季全国火災予防運動 | 11月9日から11月15日 |
| 年末火災特別警戒 | 12月20日から12月31日 |
文化財防火デー総合防災訓練「姫路城」
広報手段
姫路シティFM21(FM GENKI)での放送
- 消防局は、姫路シティFM21を防災メディアとして活用し、災害時や災害発生の恐れのある時など緊急時には、適切な情報を迅速かつ一斉に伝達したり、災害の発生状況や被害の状況など、きめ細やかな情報をリアルタイムに提供しています。
- 平常時は、地震、風水害、火災等の災害に関する豆知識、日常生活でのケガ、病気等の応急手当の方法、消防団の活動紹介や消防防災関係の訓練やイベントのお知らせを消防・防災啓発番組「わが町・元気」の中で放送しています。
姫路ケーブルテレビ(ウインク)での放送
- 「消防局からのお知らせ」で、各種資格試験、行事予定など、市民の皆さんに知ってもらいたい消防に関する情報を、放送しています。
姫路市消防音楽隊
- 姫路市消防音楽隊は、市民の皆さんに音楽を通して防火・防災情報を提供する活動を行っております。
防火指導
立入検査
立入検査は、消防対象物の自主防火管理状況を消防職員による定期的な立入検査によって確認し、火災発生危険やこれに伴う人命危険を予防させることを目的とし、消防対象物を規模や用途により区分しています。
消防同意等
消防同意とは、消防機関が防火の専門家としての立場から、建築行政等に対して、建築物の新築等の段階で防火上のチェックを行い、予防行政の目的を達成しようとするものです。
公共施設の新築等の計画については、消防同意の対象とならないものもありますが、その場合についても、消防局がその計画(計画通知)に対して消防同意と同様のチェックを行います。
防火対象物定期点検報告制度
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防機関に報告することが義務づけられています。点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
また、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、3年間点検・報告が免除されるとともに、防火優良認定証を表示することができます。
表示制度
ホテル・旅館等の宿泊施設からの申請に基づいて、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に表示マーク(「適マーク」)を交付する制度です。
宿泊施設は、表示マーク(「適マーク」)を掲出して安全安心情報を利用者に提供することができます。外国人宿泊客の増加をふまえ、表示マーク(「適マーク」)には英語・中国語・韓国語を併記しています。
防火管理
防火管理者の役割
- 消防法では、一定規模以上の建物に「防火管理者」を定め、防火管理上必要な業務を行うことが義務づけられています。
- 防火管理者制度とは、人の手による自主的な火災予防を目的としたものであり、日常における火気管理はもとより火災等の発生時の初期活動(人命の安全確保・火災の拡大防止・被害の軽減)を効果的に行うために重要な役割を果たしています。
防火管理講習
- 消防法に規定する防火管理者の資格を取得するための講習を、年間7回(甲種7回・乙種1回)行っています。また、再講習の受講義務のある建物の防火管理者に選任されている方を対象として、再講習を年間2回行っています。
住宅火災対策
住宅用火災警報器等の普及促進
- 住宅用火災警報器とは、火災の煙や熱を感知し鳴動することにより、逃げ遅れによる被害を防止するための住宅防火対策に効果的な機器のことです。
- 消防法によりすべての住宅に設置が義務付けられており、姫路市火災予防条例により設置・維持の基準が定められています。
- 実際に、「住宅用火災警報器のおかげ」で大切な命や財産を守ることが出来た、または、被害が少なくて済んだという事例が多数報告されています。
高齢者対策
- 住宅火災における犠牲者で高齢者の比率が高いことから、この種の犠牲者を一人でも少なくするため、住宅用火災警報器・住宅用消火器の設置や防炎製品などの使用を勧めたり、火気使用時の注意事項を、各種講演会・住宅訪問などの機会を通じて、市民指導を実施しています。
- また、高齢者に見やすいチラシ・ポスターを作成したり、ケーブルテレビ、新聞、各種機関誌などを活用して啓発しています。
民間防火組織の育成
- 民間防火クラブ交流委員会
今後の人口減少社会を踏まえ、各消防署(5署)単位で、婦人防火クラブや幼年消防クラブの活性化を図り、消防団とも連携した組織を結成し、地域ぐるみで災害に強いまちづくりを目指しています。 - 婦人防火クラブ
地域の安全や安心等の基盤づくりに女性の参画を促し、女性の視点や観点を活かした防災体制を確立するため結成された組織です。
女性が主体となった消防訓練や家庭防火に関する消防教室等を実施し、地域防災の要として活動しています。 - 幼年消防クラブ
幼年期から、防火の重要性や災害に対する知識を習得することで、成人してからも、火災予防や防災に対する意識を持ち続け、災害時に適切に対応できる人材を育成するため活動を行っています。
違反対象物公表制度
重大な消防法令違反のある建物について、その建物を利用する方自らが火災危険性に関する情報を入手し利用について判断ができるよう、消防法令違反を消防局ホームページに公表する制度です。
危険物規制
危険物保安体制
近年の科学技術、産業経済の発展により、危険物の態様とそれを取り巻く環境には著しい変化がみられ、それに伴い危険物に起因する災害も多様化しています。
消防局においては、危険物災害の絶滅を期するため、立入検査や講習会等の機会を通じ、危険物の貯蔵・取り扱いの実態に即した保安体制の確立を図り、併せて地震時等における危険物保有事業所の自主防災体制のより一層の充実・強化を図っています。
また、危険物の取り扱いがますます多様化する傾向の中、危険物災害の未然防止を図り、市民生活の安全を更に高めていくため、厳正な法令等の執行とともに、危険物取扱者に対する適正な指導及び査察体制の充実強化に努めています。
石油コンビナート等特別防災区域
石油コンビナート等災害防止法に基づき、姫路市の南部約18.99k平方メートルが姫路臨海地区特別防災区域に指定(昭和51年7月14日)されています。
同地区は、14事業所が特定事業所に指定され、各事業所では、防災資機材等を設置し、防災体制を確立しています。
更に、特別防災区域の防災対策を総合的・計画的に推進するため、「兵庫県石油コンビナート等防災計画」が定められています。
保安教育
危険物施設事故の原因は、管理や確認が不十分であったなど人的要因によるものが大半を占めており、なかでも作業・設備点検マニュアルの不徹底等が見受けられます。
この種の事故を未然に防止するため、危険物取扱者等に対し防災意識の高揚及び通報体制の整備充実を指導し、自主保安体制の確立を図っています。
また、毎年6月の第2週の「危険物安全週間」には、危険物安全大会を開催し、防災講演会を実施するほか、危険物安全週間ポスターの作成配布、広報媒体を通じた危険物の安全管理意識の啓発を図るとともに、各種消防訓練の実施、危険物施設の立入検査、予防規程・防災規程、各種計画等の見直し指導を行っています。
予防に関するお知らせ
姫路市消防出初式
姫路市消防出初式を姫路城三の丸広場で実施しました。当日は晴天に恵まれ、約6,000人の方が見学に来られました。式典の部では、功績のあった消防団員や事業所への表彰、部隊観閲や来賓祝辞のあと、若手消防職員が「消防の任務に情熱を注ぎ、全力でその使命を全うする」と、誓いのことばを述べました。演技の部では飾磨高校による書道パフォーマンス、消防音楽隊と「リトルフェローズバトンチーム」によるドリル演奏、消防団員によるはしご乗り演技、救助隊によるレスキュー演技や迫力のある放水演技が披露され、観衆から大きな拍手が寄せられました。
春季全国火災予防運動
期間:3月1日から3月7日
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図ることにより火災の発生を防止し、高齢者等の死傷者を減少させ、財産の損失を防ぐことを目的に実施しています。
重点項目
- 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
- 放火火災防止対策の推進
- 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
- 製品火災の発生防止に向けた取組みの推進
- 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底
- 地震火災対策の推進
野焼きに関する注意点
- 周囲に燃えやすい物がない場所で行いましょう。
- 乾燥注意報が出ている時や風が強い場合は行わないようにしましょう。
- 消火器具(水バケツ・消火器)を準備しましょう。
- 廃棄物の焼却は禁止です。
- 火を消すまではその場から離れない。
- 再び燃えださないように完全に消火しましょう。
住宅防火いのちを守る10のポイント(4つの習慣・6つの対策)
- 4つの習慣
- 寝たばこは絶対にしない、させない
- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
- こんろを使うときは火のそばを離れない
- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
- 6つの対策
- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく
- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防災対策を行う
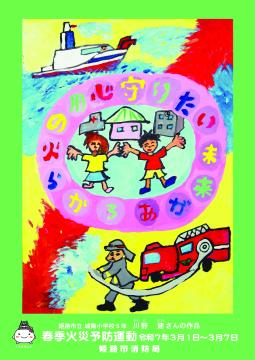
コンセントからの火災 火災の合同鑑識見分
コンセントが原因の火災が発生し、兵庫県立大学藤原名誉教授とともに合同鑑識見分を実施しました。家庭内で発生する火災の原因として多くみられるのは、たばこの不始末やこんろの他、電気に起因する火災も多く発生しています。コンセントからの火災を防ぐため、どんな原因でコンセント火災が起こるのか、必要な対策についてご紹介します。
- コンセントにプラグを差し込み長時間放置していませんか?
コンセントとプラグの間に、ホコリや異物が入り、湿気が影響して発火することがあります。定期的にコンセントからプラグを外し、掃除をするようにお願いします。 - プラグはきちんと挿さっていますか?
コンセントにプラグがしっかり挿さっていなかったりするとホコリがたまりやすくなります。接触不良の状態で使うと、接触が悪い部分が発熱し、過熱しやすい状態となります。プラグはしっかり奥まで差し込んで使ってください。 - タコ足配線をしていませんか?
コンセントには、同時に使用できるワット数(W)が定められています。ワット数の上限を超えて電気を使用すると、コンセントが発熱・発火してしまう原因になりますので注意しましょう。 - 誤ったコードの使い方をしていませんか?
その他、劣化したコードを使用したり、束ねた状態で使用しているとその部分に負荷がかかり、火災につながる恐れがあります。折れ曲がった状態や重量物の下敷きになった状態で使用することも危険性がありますので注意しましょう。
収斂(しゅうれん)火災って何?
突然ですが、収斂(しゅうれん)火災という言葉を聞いたことはありますか?火災が起こる原因として、1番に「火」を思い浮かべる方がほとんどだと思いますが、実は火がなくても太陽光と反射物があれば、簡単に火災が発生してしまいます。これが収斂火災です。実際に今年度、姫路市では、収斂火災が数件発生しています。皆さんが普段使用している日用品などが収斂火災を引き起こす原因になるかもしれません。今一度収斂火災の原理を理解し、火災予防に努めてください。
灯明に注意、ローソクが倒れて火災に発展
お盆やお彼岸など、帰省や法事の際に是非気を付けていただきたい「仏壇のローソクに潜む火災危険」についてお知らせします。「ローソク1本火事のもと」ですが、皆さんのほんの少しの注意で火事は防げます!
- ローソクに火を付けるときは、周りに燃えやすいものがないかチェックしましょう。最近では、コンセント式の電球型ローソクもあります。
- その場を離れる時は、ローソクの火を消しましょう。ちょっと離れる「だけ」、火事にならない「だろう」では手遅れです。
皆さん、火災を未然に防ぎましょう。火災予防のポイントをチェックして、おじいちゃんやおばあちゃんにも教えてあげてくださいね。
姫路東消防署御国野出張所では、管内の保育園で消防訓練指導を実施しました。訓練では、119番通報要領や避難誘導、実際に園内の安全な場所まで避難していただきました。併せて消防車の見学も行い、園児からは、消防車や火災のこと、消防職員の好きな食べ物などたくさんの質問を頂きました。災害はいつどこで起こるかわかりません。日頃から訓練や防災情報を有効に活用し、災害等の非常時に備えましょう!
中国語の消火器取扱い動画の作成
消火器は身近な消火器具であり、初期消火に大きな力を発揮します。この度中播消防署では、管内に多数の外国人労働者がいらっしゃることもあり、火災が発生した際に安全に消火器を取り扱ってもらうため、中国語の消火器取扱いの動画を作成しました。他の言語についてもいずれ作成していく予定です。内容についてのお問い合わせは、お気軽に中播消防署予防担当までご連絡ください。


 くらし・手続き
くらし・手続き 安全・安心
安全・安心 観光・文化・スポーツ
観光・文化・スポーツ 産業・経済・ビジネス
産業・経済・ビジネス 市政情報
市政情報








