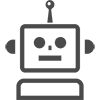麻しん(はしか)に注意しましょう
令和6年2月に国内で麻しん患者が発生し、その後も海外渡航歴がある人等を中心に、麻しん患者が発生しています。今年は去年を上回るペースで発生が報告されています。
麻しんは感染力が極めて強く、多くの人に感染します。海外での滞在歴や麻しん患者との接触があり、麻しんを疑う症状が出現した場合には、速やかに事前に医療機関へ連絡し受診の相談をしてください。また、受診の際は、公共交通機関の利用は控えましょう。
麻しんを疑う症状がない場合でも、最近の海外渡航歴や麻しん患者との接触がある方は、2週間は健康観察を十分に行ってください。
麻しんとは
麻しんは、一般的には「はしか」と呼ばれている急な発熱、上気道症状、発疹を主な症状とする感染力が極めて強い感染症です。麻しんの潜伏期間は約10日から12日といわれており、一旦発症すると、中耳炎、気管支炎、肺炎、脳炎等を合併し重症化することがあります。稀ではありますが、重症の場合は肺炎や脳炎で死亡することもあるといわれています。
- 麻しんはワクチンで予防することが可能です。しかし、麻しんの予防接種を受けたことがあっても、100人に2人から3人は、免疫が十分に獲得できない場合があります。
- 麻しんの初期症状は、風邪様症状と似ていますので、発熱等がある方は、外出を控え、症状がある場合は早めに医療機関を受診してください。
- 治療方法としては、麻しんウイルスの特効薬はなく、解熱剤やせき止めなどの対象療法しかありません。脱水や、ビタミン欠乏になりやすいので、水分や栄養の補給を心がけましょう。主治医の指示に従い、しっかり休養を取ってください。
麻しんを予防するには
日常的な感染症対策として、外出から帰ったら、うがい、手洗いを励行することは大切です。また、人混みに出る場合には、マスクを着用することも効果があります。また、麻しんにはワクチンがあるため、麻しんの予防接種をすることが麻しんに対する最も有効な予防法と言えます。
麻しんの予防接種
麻しん含有ワクチン(主に接種されているのは、麻しん風しん混合ワクチン)を接種することによって、95%程度の人が麻しんウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。また、2回の接種を受けることで1回の接種では免疫が付かなかった方の多くに免疫をつけることができます。
姫路市では、こどもの定期予防接種に麻しん風しん混合(MR)ワクチン(風しん罹患者は麻しん単抗ワクチン)の接種があります。定期接種の対象になるかは、姫路市で受けることができるこどもの定期予防接種の一覧をご確認ください。
定期接種の対象外で、過去に麻しんの感染歴がなく、麻しんの予防接種歴もないまたは不明な方は、麻しんの予防接種を、任意(費用は自己負担)で受けることができます。接種については、主治医にご相談ください。抗体検査や予防接種にかかる費用は自己負担になります。費用は医療機関毎に異なるため、受診される医療機関に確認してください。
流行地に行く場合などは特に注意が必要です
日本は、平成27年3月27日、世界保健機関西太平洋地域事務局により、麻しんの排除状態にあることが認定されました。かつては毎年春から初夏にかけて流行が見られていましたが、排除後は、海外からの輸入例と、輸入例からの感染事例のみを認める状況となっています。
海外では、麻しんが流行している国があり、また、渡航先だけでなく空港でも、いろいろな国の人と接する機会がありますので、注意が必要です。麻しんにかかった(検査で診断された)ことがない方が海外渡航される時には、あらかじめ麻しんの予防接種歴を確認し、麻しんの予防接種を2回受けていない場合、又は接種既往が不明の場合には予防接種を受けることを検討してください。
世界における麻しんの流行状況
麻しん(はしか)のQ&A
麻しん(はしか)について、よくあるご質問とその答えをQ&A形式でお知らせします。
麻しんはどんな症状ですか?
始めの3日から4日(カタル期)は38度前後の発熱、咳、鼻水、結膜充血などで、<かぜ>と区別がつきません。その後いったん熱が下がり、4から5日(発疹期)後、再び高熱が出て、赤い小さな発疹が、耳の後ろから顔面に出はじめて次第に手足などに広がります。乳幼児では、下痢、腹痛等の消化器症状を伴うことが多くあります。
麻しんはどのようにして感染しますか?
空気感染や飛沫感染します。
麻しんは、いつ頃はやりますか?
季節的な傾向としては、初春から初夏にかけて患者が多く発生しますが、1年をかけて感染する可能性があります。
コロナ禍後、流行していますか?
コロナ禍では、海外渡航の禁止により麻しん含め他の感染症の流行が抑えられていた状況でしたが、海外渡航が活発化してきた2023年4月下旬から発生があり、近畿地方でも複数名の麻しん感染者の報告があります。かつては毎年春から初夏にかけて流行が見られていましたが、2015年、WHOは、日本において麻しん排除状態であると認定しました。その後は、海外からの輸入例と、輸入例からの感染事例のみを認める状況です。コロナ禍後の国際交流の活発化は今後も続きますので、小規模ながらも輸入症例による国内感染流行が見られると推測されます。
周期的に流行しますか?
過去、麻しんワクチン接種率が低い頃には、乳幼児を中心に流行がありましたが、現在は麻しん風疹ワクチン接種により免疫を獲得している人が増え、大規模な流行は抑えられていますが、現在は海外渡航者が増加しており、麻しんの持ち込みによる感染流行が、規模は小さくても定期的にみられると予想されます。
麻しんにかかったと思ったらどうしたらいいですか?
早めに医療機関を受診することをお勧めします。特に麻しんの予防接種を受けていない場合や過去に麻しんに感染したことがない場合(特に乳幼児や高齢者の方)は、重症化することがあります。重症化すると、肺炎、腸炎、中耳炎、脳炎などの症状が現れます。脳炎症状が出た患者では、麻痺などの後遺症を残す場合があると言われています。
学校等への出席の可否
学校保健安全法第19条では「校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑があり、またはかかるおそれのある児童、生徒、学生または幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」となっています。(学校教育法第1条に定められている法定学校とは小、中、高校、大学、高専、盲・聾・養護学校、幼稚園等を指します。)
学校における麻しんの出席停止の基準は「発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで」となっています。出席停止の決定を行うのは校長ですので、個別のケースについては学校等にご相談ください。
麻しんに感染しないようにするためには、どうしたらいいですか?
予防接種を受けていない場合や過去に麻しんに感染したことがない場合は、予防接種を受けることをお勧めします。外出から帰ったら、うがい、手洗いを励行することは重要です。また、人混みにでる場合にはマスクを着用することも効果があります。
予防接種を受ける場合、費用はどのくらいかかりますか?
定期予防接種の対象者(注)は無料で接種を受けることができますので、詳細については、姫路市で受けることができる定期予防接種一覧のページをご覧ください。
定期予防接種の対象者以外でも、接種を希望する場合には自費で受けることができますが、医療機関によって費用が異なりますので、医療機関に問い合わせてください。
(注)予防接種法の一部が改正され、平成18年4月1日から施行されました。この改正により、麻しんの定期予防接種は、麻しん風しん混合ワクチンによる2回接種となり、定期予防接種対象者は次のとおりとなりました。
- 第1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
- 第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達するまでの日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者(いわゆる幼稚園の年長児)
兄弟姉妹の1人が麻しんにかかったが、他の兄弟姉妹に感染しないのか心配です。
麻しんの予防接種を受けていない場合や過去に麻しんに感染したことがない場合には、麻しんの予防接種を受けることをお勧めします。
なお、定期の予防接種の対象者であれば、費用は無料となります。定期の予防接種の対象者以外でも、希望すれば自費で予防接種が受けられますので、医療機関にご相談ください。
麻しんの潜伏期間は一般的に10日前後と言われています。この間に風邪様の症状がでた場合には、早めに医療機関を受診してください。
予防接種を受けていても感染することがありますか?
予防接種を受けていても感染する場合があります。しかし、感染しても予防接種を受けたことがない人に比べ、一般的に症状は軽く済むと言われています。
麻しんの予防接種は、いつ頃から始まりましたか?
麻しんの定期予防接種は1978年(昭和53年)10月から始まりました。このため、1978年以降に定期予防接種の対象者に該当しない人は、麻しんの予防接種を受けていない可能性があります。
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所健康福祉局保健所保健所防疫課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1721 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!