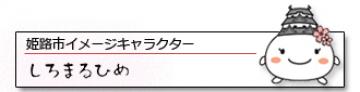関ノ口遺跡18次発掘調査の現地説明会を実施します!
- 更新日:
- ID:28560
資料提供日
令和6年8月22日(木曜日)
問い合わせ先
担当課 姫路市埋蔵文化財センター
担当者 南・山下
電話番号 079-252-3950
現地説明会開催日時
令和6年8月31日(土曜日) 午前10時00分から(少雨決行、雨天中止)
開催場所
姫路市網干区和久地内(添付資料の調査位置図参照)
遺跡の概要
今回の調査地は関ノ口遺跡に該当し、JR網干駅周辺の区画整理事業に伴って実施しました。当遺跡は、弥生時代から中世にかけての集落遺跡です。過去の調査では縄文土器も出土しており、姫路市を代表する遺跡の一つです。
調査の概括事項
- 調査名:関ノ口遺跡第18次発掘調査
- 調査期間:令和6年6月25日(火曜日)から令和6年9月下旬予定
- 面積:384平方メートル
- 調査原因:JR網干駅周辺の区画整理事業
- 主な成果:竪穴建物跡12棟、掘立柱建物跡1棟、溝1条ほか
調査の成果
今回の調査を行った箇所は、以前の調査で確認された弥生から古墳時代の柵の内側にあたります。今回の調査では、弥生時代中期から古墳時代にかけての竪穴建物跡12棟、古墳時代以降と考えられる掘立柱建物跡1棟とおよそ直角に折れ曲がって延びる溝1条などを確認しました。
竪穴建物跡 確認した12棟は、いずれも弥生時代中期から古墳時代にかけてのものです。平面形は方形・円形・多角形の可能性があるものが見つかっています。
- 竪穴建物跡2・3 1辺約4.2mを測る方形の竪穴建物跡です。建物跡南西部で平行する2条の周壁溝が見つかったことから、およそ同じ位置で、建て直しが行われたと考えられます。主柱穴は3基確認しました。竪穴建物跡6とおよそ平行する位置でみつかりました。
- 竪穴建物跡8 平面形は、検出部分の特徴から円形と想定できます。床面では、焼土の塊や炭化した木材が見つかりました。このことから何らかの原因による火災で焼失したものと考えられます。詳細な時期は不明ですが、竪穴建物跡2・3との重なりから、それらより古いと考えられます。
- 竪穴建物跡9 平面形は、円形または多角形と考えられます。竪穴建物跡2・3との重なりから、それらより古いと考えられます。見つかった土器から弥生時代中期から後期と考えられます。
- 竪穴建物跡12 平面形は方形と考えられます。竪穴建物跡8と同様、焼失した痕跡がみられます。また掘立柱建物跡との重なりから掘立柱建物跡よりも古いと考えられます。
掘立柱建物跡 桁行3間×梁行2間(約6m×約3.5m)で、柱間は約1.5mを測ります。後世の撹乱によって一部の柱穴は失われていましたが、総柱建物であった可能性が考えられます。総柱建物は、側柱建物よりも柱が多いため頑丈であり、倉庫などに利用された可能性が考えられます。掘立柱建物跡の詳細な時期は不明ですが、一部の柱穴から須恵器が見つかったため古墳時代以降のものと考えられます。
溝 総延長約9mを測り、北東隅と南東隅でおよそ直角に折れ曲がりコの字状を呈します。溝の断面形は方形で、人工的に掘られたと考えられます。溝の性格は判然としませんが、掘立柱建物跡とおよそ平行する位置にあるという特徴がみられます。このことから溝と掘立柱建物跡は同時期に機能した可能性も考えられます。
調査の意義
今回の調査では、平面形や規模が異なる弥生時代中期から古墳時代の竪穴建物跡を12棟発見しました。その半数以上は、重なり合っていたことから、その時代に生きた人々が同じ場所で自らの住まいを建て替えながら生活していた様子がうかがえます。このことは、関ノ口遺跡におけるこれまでの調査成果とも合致します。また、倉庫などの可能性がある掘立柱建物跡や、それと平行するコの字状の溝も確認しました。さらに調査区南側では、谷地形の落ち込みを確認しました。
特に、柵の内側と想定される場所に竪穴建物跡が集中するとともに、倉庫などの可能性がある建物跡が見つかったことは注目されます。また、谷地形の落ち込みは、これまでの調査でも確認しており、集落が地形的に高い場所に形成されていたことが明らかになりました。
現地説明会会場へのアクセス・その他
- JR網干駅から北へ徒歩約3分。
- 少雨決行。雨天中止。
- 駐車場はありません。
- 歩きやすい服装・靴でお越しください。
- 帽子や水筒等をご持参のうえ、熱中症には十分ご留意ください。
添付資料
お問い合わせ
姫路市 教育委員会事務局 生涯学習部 埋蔵文化財センター
住所: 〒671-0246 姫路市四郷町坂元414番地1別ウィンドウで開く
電話番号: 079-252-3950
ファクス番号: 079-252-3952

 くらし・手続き
くらし・手続き 安全・安心
安全・安心 観光・文化・スポーツ
観光・文化・スポーツ 産業・経済・ビジネス
産業・経済・ビジネス 市政情報
市政情報